GaAs宯敿摫懱嵽椏丂擔棫崙嵺尋媶僠乕儉傪嵦梡
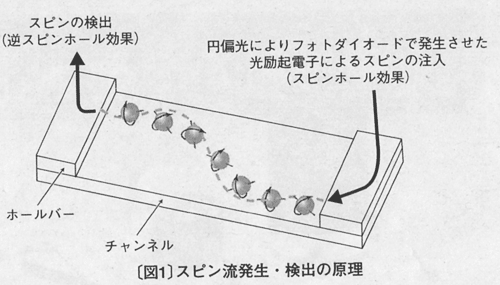
丂擔棫惢嶌強偼丄墷廈偵偍偗傞尋媶奐敪嫆揰偱偁傞擔棫儓乕儘僢僷幮擔棫働儞僽儕僢僕尋媶強傪偼偠傔偲偡傞崙嵺尋媶僠乕儉偑丄僈儕僂儉僸慺乮俧倎俙倱乯宯偺敿摫懱嵽椏傪梡偄偰丄揹巕偑傕偮帴愇偺惈幙偱偁傞僗僺儞偺棳傟乮僗僺儞棳乯傪揹棳偲摨條偵惂屼丒娤應偡傞偙偲偵惉岟偟偨偙偲傪敪昞偟偨丅俀侽悽婭偺嶻嬈傪敪揥偝偣偨揹巕偺揹壸偺棳傟乮揹棳乯傪棙梡偡傞僄儗僋僩儘僯僋僗媄弍偵懳偟偰丄偙偺媄弍偼揹巕偑帩偮傕偆堦偮偺惈幙偱偁傞僗僺儞傪棙梡偡傞僗僺儞僩儘僯僋僗媄弍偵摴傪奐偔惉壥偱偁傞丅
僗僺儞僩儘僯僋僗奐敪偺攚宨
丂
侾俋係侽擭戙偵僩儔儞僕僗僞偑敪柧偝傟偰埲棃丄僄儗僋僩儘僯僋僗嶻嬈偺敪揥偵峷專偟偰偒偨揹巕僨僶僀僗偼丄揹巕偺暔棟揑惈幙偱偁傞揹壸偺棳傟乮揹棳乯傪棙梡偟偰偒偨丅揹巕偵偼丄揹壸偲偲傕偵丄忋岦偒偲壓岦偒偺俀庬偺抣偑偁傞僗僺儞偲屇偽傟傞帴愇偺惈幙偑偁傞丅捠忢偺揹巕偵偍偄偰偼俀庬偺僗僺儞偼俆侽亾偺妋棪偱娷傑傟偰偄傞偨傔丄僗僺儞偺摿惈偼尠嵼壔偟側偄丅揹巕偑傕偮僗僺儞偺惈幙傪棙梡偡傞僗僺儞僩儘僯僋僗傪梡偄傞偙偲偵傛傝丄揹巕僨僶僀僗偺侾/侾侽乣侾/侾侽侽偲傕尵傢傟傞戝暆側掅揹椡壔傗丄揹婥丒帴婥梈崌僨僶僀僗側偳丄廬棃偺揹巕僨僶僀僗偱偼幚尰偱偒側偐偭偨婡擻傪傕偮僨僶僀僗偺奐敪偑婜懸偱偒傞丅揹巕偺僗僺儞棳傪揹婥揑偵惂屼丒娤應偡傞棟榑偼丄栺俀侽擭慜偵採埬偝傟偰偄傞偑丄偦偺幚徹偵偼丄僗僺儞棳偺拲擖丄惂屼丄娤應側偳丄僗僺儞僩儘僯僋僗偵昁恵偺婎慴尰徾傪嶌傝弌偡昁梫偑偁傞丅偟偐偟丄尰嵼偵帄傞傑偱丄僗僺儞棳傪揹棳偲摨條偵恖岺揑偵惂屼丒娤應偟偨帠椺偼側偐偭偨丅
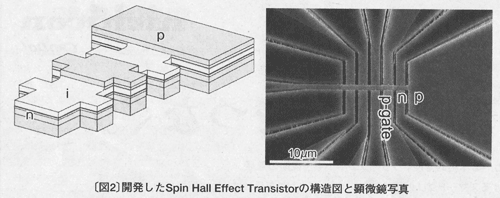
擔棫崙嵺尋媶僠乕儉偺庢傝慻傒
丂
偙偺傛偆側攚宨偐傜丄擔棫傪偼偠傔偲偡傞崙嵺尋媶僠乕儉偼丄僗僺儞僩儘僯僋僗偺幚梡壔偵岦偗偰丄傑偢俀侽侽俆擭偵帴惈嵽椏傪梡偄偢偵俧倎俙倱宯敿摫懱偱丄儅僀僫僗俀俇俋亷偺嬌掅壏偵偍偄偰忋岦偒丒壓岦偒僗僺儞偺娤應乮僗僺儞儂乕儖岠壥偺娤應丗僗僺儞婳摴憡屳嶌梡傪桳偡傞暔幙拞偵揹棳傪棳偟偨偲偒丄揹棳楬偺椉抂偵忋岦偒僗僺儞傪桳偡傞揹巕偲丄壓岦偒僗僺儞傪桳偡傞揹巕偑暘棧偟偰拁愊偡傞尰徾偺娤應乯偵惉岟偟偨丅俀侽侽俋擭偵偼丄摨偠偔俧倎俙倱慺宯敿摫懱偱丄儅僀僫僗俆俁亷偵偍偄偰悢兪倣偺嫍棧傪堏摦偡傞僗僺儞棳偺娤應偵惉岟偟偰偄傞丅偙傟偼僗僺儞僀儞僕僃僋僔儑儞儂乕儖岠壥偲尵傢傟丄塃嵍偺屻弎偺墌曃岝傪梡偄偰敿摫懱拞偵椼婲偟偨忋岦偒乛壓岦偒僗僺儞傪丄僗僺儞儂乕儖岠壥偱専弌偡傞曽朄偱偁傞丅
奐敪偟偨僗僺儞棳惂屼慺巕偺奣梫
丂
崱夞丄奐敪偵惉岟偟偨慺巕偼俧倎俙倱宯敿摫懱傪梡偄偰丄倫値愙崌傪桳偡傞暯柺宆僼僅僩僟僀僆乕僪偲儂乕儖岠壥傪應掕偡傞偨傔偺僨僶僀僗偱偁傞儂乕儖僶乕傪宍惉偟偨値宆僠儍僱儖偐傜峔惉偝傟偰偄傞丅僼僅僩僟僀僆乕僪偵岝傪偁偰丄岝婲揹椡岠壥偱惗偠傞岝椼婲揹巕偵傛傝丄僗僺儞傪慺巕偵拲擖偡傞丅擖幩偡傞岝偼僗僺儞傪堦掕偺曽岦偵懙偊偨僗僺儞曃嬌揹巕傪惗惉偡傞偨傔偵墌曃岝傪梡偄傞丅
丂
岝偼揹応傗帴応傪揱斃偡傞攇偱偁傞偑丄曃岝偟偰偄傞岝偲偼丄揹応偍傛傃帴応偑摿掕偺曽岦偵偟偐怳摦偟偰偄側偄岝偺偙偲偱偁傞丅杮尋媶偱偼墌曃岝傪梡偄偰偄傞丅偙偙偱丄墌曃岝偲偼丄揹帴攇偺怳摦偑揱攄偵敽偭偰墌傪昤偔傕偺偱丄夞揮曽岦偵傛偭偰丄塃墌曃岝偲嵍墌曃岝偑偁傝丄曃岝妏搙偲偼夞揮偺妏搙偱偁傞丅
丂
偙偺傛偆偵偟偰拲擖偝傟偨僗僺儞偼丄夞揮偟偰偄傞撈妝偺塣摦偺傛偆偵帺揮偟偰偄傞暔懱偺夞揮幉偑墌傪昤偄偰怳傟偰偄傞嵨嵎塣摦傪偟側偑傜僗僺儞棳偲側偭偰堏摦偡傞乮僗僺儞僀儞僕僃僋僔儑儞儂乕儖岠壥乯丅偙偙偱値宆僠儍僱儖偺忋偵倫宆偺揹嬌傪宍惉偟丄揹埑傪壛偊傞偲丄憡懳榑揑検巕榑岠壥偵傛傝丄僎乕僩揹嬌偵偍偗傞僗僺儞偺嵨嵎塣摦偑惂屼偝傟傞丅偙傟偵傛傝丄暿偺儂乕儖僶乕偱専弌偝傟傞僗僺儞偺岦偒丄偡側傢偪揹埑偑惂屼偝傟傞偙偲偵側傞丅
丂
惂屼偺僇僊偱偁傞憡懳榑揑検巕榑岠壥偲偼偙偙偱偼僗僺儞丒婳摴憡屳嶌梡偺偙偲傪巜偡丅憡懳榑揑検巕岠壥傪巊偆偲丄帴応偑壛傢偭偰偄側偄忬懺偱傕丄揹応偵懳偟偰悅捈偵摦偄偰偄傞揹巕偵偼丄揹応埲奜偵帴応偑崿偠偭偰偄傞傛偆偵尒偊傞尰徾偑摫偒弌偝傟傞丅偙傟偵僗僺儞偑塭嬁傪庴偗丄僗僺儞偺岦偒偵傛偭偰恑峴曽岦偑嬋偘傜傟傞丅偙傟偑丄僗僺儞婳摴憡屳嶌梡偱偁傝丄崱夞偺僨僶僀僗偺僇僊傪扴偭偰偄傞
丂 俧倎俙倱宯敿摫懱偵拲擖偟偨僗僺儞棳偺忋岦偒丒壓岦偒傪揹埑偱惂屼偱偒傞慺巕傪奐敪偟丄僆儞丒僆僼摦嶌傪娤應偡傞偙偲偵惉岟偟偨丅幚尡偱偼丄岝偺墌曃岝傪棙梡偟偰敿摫懱偵僗僺儞傪拲擖偟偰偄傞偑丄崱屻丄嫮帴惈懱嵽椏偵偍偄偰僗僺儞傪拲擖偡傞媄弍偑奐敪偱偒傟偽丄侾俋俋侽擭偵俽倳倫倰倝倷倧丂俢倎倲倲倎偲俛倝倱倵倎倞倝倲丂俙丏俢倎倱偑棟榑梊應偟偨僗僺儞僩儘僯僋僗僨僶僀僗偑幚尰偱偒傞丅
丂 傑偨丄岝偺曃岝傪惂屼丒娤應偱偒傞屌懱僨僶僀僗傪奐敪偟偨偙偲偼丄岝偺曃岝妏偲偄偆忣曬傪壛偊偨戝梕検忣曬捠怣僔僗僥儉傪幚尰偡傞壜擻惈傗丄惗懱丒崅暘巕嵽椏偺摿惈傪岝偺曃岝偱暘愅偡傞怴偨側専嵏僔僗僥儉側偳偺奐敪偵偮側偑傞惉壥偱偁傞丅偝傜偵丄峀斖偵彨棃偺幮夛僀儞僼儔偵偍偗傞戝暆側徣揹椡壔丒崅婡擻壔傗検巕僐儞僺儏乕僞傪偼偠傔偲偡傞壢妛偺怴偨側敪揥偵峷專偡傞偙偲偑婜懸偱偒傞丅
丂 杮惉壥偼嶐擭侾俀寧俀係擔敪峴偺暷崙俽們倝倕値們倕帍乮倁倧倢丏俁俁侽丆噦俇侽侾俀丆倫倫丏侾俉侽侾儅僀僫僗侾俉侽係乯偵宖嵹偝傟偨丅
丂 側偍丄崙嵺尋媶僠乕儉偼擔棫儓乕儘僢僷幮働儞僽儕僢僕尋媶強丄僠僃僐壢妛傾僇僨儈乕丄僠儍乕儖僘戝妛乮僠僃僐乯丄働儞僽儕僢僕戝妛乮塸乯丄僲僢僥傿儞僈儉戝妛乮塸乯丄僥僉僒僗俙仌俵戝妛乮暷乯偱峔惉偝傟偰偄傞丅
丂
亙帒椏採嫙丗俽們倝倕値們倕帍丄乮姅乯擔棫惢嶌強亜